すべて表示する
メールマーケティングとは
メールマーケティングとは、Eメールによってコミュニケーションをとることで、集客やコンバージョン達成、見込み客の育成を目指すマーケティング手法です。
一般的なデジタル広告と比べたメールマーケティングの特徴は、低コストで取り組み可能な点と、配信先の属性に合わせて配信の内容やタイミングをカスタマイズし、きめ細やかなコミュニケーションができる点にあります。
メールマーケティングが未だに重要な理由
SNSやチャットアプリの普及によって、「メールはもう古いマーケティング手法」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、メールの利用者数は依然として多く、未だに有力なマーケティング施策のひとつであり続けています。
総務省が2023年6月に発表した「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によれば、30代以上の世代では平日のメールとSNSの利用量は僅差であり、40代以上はSNSの利用率よりメールの利用率の方が高いとされています。
出典:『情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書』(総務省 - 2023年6月)
メールマーケティングの種類
メールマーケティングといえば「メルマガ」を思い浮かべる方も多いと思いますが、メルマガはメールマーケティングのごく一部でしかありません。
メールマーケティングには、ステップメール、シナリオメール、ターゲティングメール、リターゲティングメールなど、さまざまな手法があります。
ターゲティング | 配信タイミング | 難易度 | |
メルマガ | しない | 定期的 | 低 |
ステップメール | しない | 段階的 | 中 |
シナリオメール | しない | 段階的 | 高 |
ターゲティングメール | する | スポット | 中 |
リターゲティングメール | する | スポット | 中 |
メルマガ
登録しているユーザーに対してニュース・キャンペーンなどの情報を一斉送信するメールのことです。
定期的に配信しますが、時間や頻度は発信側が自由に決められます。
定期的に送ることで受信側の企業・商品理解が深まり、ユーザーのファン化が期待できる一方で、画一的な内容になってしまうため、直接コンバージョンにつなげることは難しいという面もあります。
求めていない情報が頻繁に送られてくれば、煩わしく思って購読をやめてしまうこともありますので、どのような情報を、どのくらいの頻度で、どのようなタイミングで送るか受信者側の状況も踏まえて配信する必要があります。
ステップメール
ステップメールは「段階的に配信する」メールです。フォローアップメールともいわれます。
受信者の関心や検討度合いが変化しやすいタイミングをあらかじめ予想して、検討段階にあった情報を自動で配信する設定を行います。
たとえば、自社サイトのカタログをダウンロードしてくれた見込み客に対してのメール配信スケジュールは以下のようなものが考えられます。
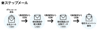
- ダウンロード直後→お礼メール
- 1通目配信から3日後→自社製品の導入事例
- 2通目配信から3日後→他社製品との比較データ
- 3通目配信から3日後→割引キャンペーン案内
カタログのダウンロード直後に割引キャンペーンの案内を送っても、この段階では検討が不十分なことも多く、購入にまでつながらない可能性が高いです。
ステップメールで段階的に、情報を提供することで徐々に購買意欲を高めつつ、接触回数が増えることで自社を意識してもらうことができます。
シナリオメール
受信者の行動をもとに次に配信する内容を自動で変更する手法です。
ステップメールと同様に段階的にメールを配信する手法ですが、単に段階をふむだけでなく、受信者の行動を指標にして配信内容を振り分ける高度な運用です。
例えば、ステップメールのスケジュールに受信者の行動という観点を加えると以下のようになります。

- ダウンロード直後→お礼メール
- 1通目配信から3日後→自社製品の導入事例
→A.メール内のリンクからWebサイトの商品詳細ページを閲覧→③を配信せず④へ
→B.メール未開封→別の導入事例を再度配信→3日後③を配信 - 2通目配信から3日後→他社製品との比較データ
- 3通目配信から3日後→割引キャンペーン案内
ユーザーの行動を踏まえた「シナリオ」をあらかじめ設定しておくことで、ユーザーにとって最適な情報を最適なタイミングで配信できるようになるため、高い開封・クリック・コンバージョン率を期待することができます。
一見万能に見えるシナリオメールですが、欠点は多様なユーザー行動に対応した複雑なシナリオを設計するのが難しい点です。また、指標となるユーザー行動を測定してメール配信システムに受け渡すために専用のツールを導入する必要がある場合もあります。
ターゲティング(セグメント)メール
見込み客の属性を分けて管理し、条件にあう見込み客にのみメールを配信する手法です。
見込み客の興味に近い内容を提供しやすいので、高い開封・クリック・コンバージョン率を期待することができます。
例えば、東京で行われるイベントで化粧品の実演販売を行う場合、イベントへの出展を告知するメールは「関東在住」「女性」という属性を持つ見込み客に絞るのが効果的です。
その他「Webサイトの特定のページを閲覧している」「過去に購入経験がある」「資料ダウンロードをしたことがある」など見込み客の行動を記録しておくことで、より詳細なセグメント分けを行うことができます。
リターゲティングメール
Webサイトやモバイルアプリでの行動が特定の条件を満たした見込み客に対し、条件に適した内容のメールを配信する手法です。
例えば、「Webサイトでサービス詳細ページを閲覧した見込み客に導入事例や製品比較データを送る」「カートインしたまま離脱した会員に割引クーポンの案内を送る」などの対応をします。
見込み客の行動に合わせて必要な情報を提供できるので、高い効果を期待できるのが長所です。
一方で頻度や具体性が高すぎると見込み客に「行動を監視されている」という不快感や不安感を与えることもあるので注意が必要です。
その他
その他のマーケティング手法として、お知らせや通知を配信するといったものもあります。
また、休眠顧客発掘のためにメールを行うこともあります。
過去に商談成立まで行きそうであったものの、何らかの事情で離脱してしまった見込み客や、一定期間動きのない見込み客に対してアクションを促すものです。
休眠顧客は、過去にはある程度の自社や製品に興味があった見込み客ですので、新規の顧客を探すよりも成約につながる可能性が高いです。
施策として非常に効果的なこともあり、多くの企業で積極的に行われている手法です。
メールマーケティングのメリット
コストが低い
メールマーケティングは他の広告媒体に比べて、制作・出稿のコストが低く抑えられます。
効果測定ができるメール配信システムの導入には費用が掛かりますが、配信やコンテンツ制作を内製化しやすいので、月に数万件のメールを配信しても月額費用を数千~数万で抑えることもできます。印刷代や郵送料などが掛かるダイレクトメールと比べてもかなりの低コストです。
効果測定がしやすい
効果測定ができるメール配信システムを導入すれば、開封率やクリック率コンバージョン率はもちろん、ツールによってはリンクをクリックした後のWebサイトでの行動もトラッキングできます。
ユーザーの行動を詳細に知れるため、ニーズを把握できますし、施策の改善点も見つけやすくなります。
タイムリーなアプローチができる
メールの内容や配信するタイミング、配信先は任意で選べるため、見込み客の興味や関心が高まったタイミングでアプローチをかけることができます。
定員制のセミナーに空きが発生した際や急遽実施が決まったキャンペーンを即座に告知できる点も魅力です。
ただし、見込み客一人一人に個別のアプローチをかけるには、高度な分析を行えるツールを活用する必要があります。
見込み客の育成(ナーチャリング)ができる
Googleが2022年2月に発表したレポート「Google Ads Benchmarks for YOUR Industry [Updated!]」によると、見込み客平均獲得単価(CPL:Cost Per Lead)は7,000〜1万5,000円/1見込み客とされています。
実際には、営業担当者は商談につながりやすい見込み客に優先的にアプローチをかけるので、受注確度の低い見込み客は放置されがちです。
せっかくこれだけのコストをかけてセミナーや広告から見込み客を獲得しても、これでは宝の持ち腐れです。
そこで、メール配信によって定期的に情報を提供することで、徐々に関心を高めつつ、自社を意識してもらう手法(リードナーチャリング)が効果的です。
仮に見込み客の獲得単価1万円とした場合、受注率が10%ならば受注あたりの獲得単価は10万円です。しかし、受注に至らなかった90%のリードのうち、5%でも掘り起こすことができたならば受注率は14.5%に、受注あたりの獲得単価は約7万円まで改善できます。
わずか5%の見込み客掘り起こしが受注率と受注あたりの獲得単価を大きく改善する
リード獲得単価 | 受注率 | 受注あたりの獲得単価 | |
リードナーチャリングを実施した場合 | ¥10,000 | 10% | ¥100,000 |
リードナーチャリングを実施しなかった場合 | ¥10,000 | 14.5% | ¥68,900 |
メールマーケティングのコストが低いこともあって、これは非常に大きなメリットとなります。
メールマーケティングの手順
①目標設定
まずはメールを配信する目的をもとに具体的な目標を明確にします。
例えばKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)として、「メール経由での資料請求◯件/月」としたならば、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)には、そこから逆算して「メール開封率」や「クリック率」を設定します。
ここで意識しておきたいのが、KPIとなるべき「メール開封率」や「クリック率」をKGIとしないことです。
メールマーケティングの目的は、「メールを読んでもらうこと」ではなく、あくまでその先での行動を促すことです。
わかり易い指標である「メール開封率」や「クリック率」だけを追いかけて、「リピートオーダーを増やす」「休眠顧客を掘り起こす」といった最終的な目標を見失わないようにしましょう
②配信リスト作成
設定した目標を達成するために必要な人数を計算して、メールアドレスをリスト化します。
実はここがメールマーケティングのネックとなる場合も多いです。
メールマーケティングは実施にかかるコストは低いですが、質の高いリストの作成は容易ではありません。
BtoB企業における最も典型的なリスト作成の方法は、「営業が保有している名刺のデータ化」です。名刺に特化したスキャナー等を活用してください。
BtoC企業の場合は会員データが拠り所となるでしょう。EC等のデジタルチャネルを保有していない場合は、メールマーケティングに備えて意識的に顧客からメールアドレスを収集する体制を整える必要があります。
オプトインへの対応について
メール配信を行う際の注意しなければならないのが「メールを受け取ることに同意したユーザーにのみ配信できる」点です。
これは「オプトイン方式」といって、2008年12月の「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の改正以降は義務化されています。
違反した場合、法人ならば「行為者を罰するほか、法人に対して3,000万円以下の罰金」が課せられることがあります。
メールマーケティングに向けてWebサイトなどから新たにリストを収集する場合は、会員登録の際にメール受信の同意に関する項目を設けましょう。
※オプトイン規制の例外
オプトインの義務化で「営業の持っている名刺からリストを作成するのはまずいのでは?」と疑問に思った方も多いと思います。
ご安心ください。
以下の場合は例外として事前の同意を得ずにメールを配信することができます。
- 電子メールアドレスの通知をした人
- 取引関係にある人
- 自己の電子メールアドレスを公表している団体又は営業を営む個人
企業が取引先やセミナーで交換した名刺から配信リストを作成する場合は、これらのいずれかの条件を満たす場合がほとんどですので、問題なくメールマーケティングの施策対象とすることができます。
③メールの作成
実際に配信するメールを作成します。
配信するコンテンツを作成するために、どのような相手にメールを配信するのかを明確にする「ペルソナ設定」とどのタイミングでどのような情報を欲しがるかを想定するための「カスタマージャーニー」を設定します。
カスタマージャーニーをもとに、見込み客の段階ごとに提供するコンテンツを用意していきます。
また、カスタマージャーニーをもとに、ユーザーの行動を想定できればシナリオメールやステップメールを配信することもできるようになります。
メールに表示する義務がある項目
メール配信を行う場合、送信者は以下の項目を表示することが義務付けられています。
- オプトアウト(受信解除)の通知ができること
- オプトアウト(受信解除)ができることを通知する文言
- 送信者の氏名もしくは名称
- 送信者の住所
- 苦情や問い合わせ等を受け付けるための電話番号・メールアドレス・URL
- 送信者のメールアドレスなどの連絡先
ただ表示義務はありますが、メール内に記載されていれば任意の場所に配置してよい項目ですので、フッターや署名欄にまとめて表示する場合が多いです。
記載例と注意点を日本データ通信協会が作成しているのでよく確認しておきましょう。

④メールの配信
用意したコンテンツを配信する際は、配信リストの中の誰に送るか、いつ送るかが重要です。
特に配信時間には気を使う必要があります。
メールを読まれやすい時間帯というものがあり、仕事用ならば、朝の出勤時間と昼休憩以降の時間が読まれやすくプライベートでは21時以降が最も読まれやすいという傾向があります。
これは業種や製品によっても異なりますが、メルマガ配信をする場合は想定しているペルソナの行動時間も想定して読まれやすい時間に送るようにしましょう。
例えば、40代女性用の化粧品に関するメールならば、料理や子供の世話が落ちつく21時頃に送る。
会社員の男性向けの商品ならプライベートで使う製品でも出勤時間の朝7~9時を狙うといった具合です。
メール配信時に必ず設定しておきたい「SPF」「DKIM」「DMARC」
メールに記載する送信元メールアドレスは、容易に詐称することができます。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の第五条・第六条で「送信者情報を偽った送信」および「架空電子メールアドレスによる送信」は禁止されています。
しかし、実在する企業のメールアドレスを騙って迷惑メールやフィッシングメールを送信する行為は後を絶ちません。
そのため「SPF(Sender Policy Framework)」「DKIM(DomainKeys Identified Mail)」「DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance)」といった技術で送信元詐称の疑いがあるメールを検出する仕組みが普及しています。
「SPF」は、送信元メールサーバーが正当なものかどうかを判別する技術です。
具体的な手法としては、まず送信者側がDNSサーバーにメール送信時に使うサーバーのIPアドレスを登録します。
メールを受信した際、記載されているメールアドレス(ドメイン)が登録されているサーバーのIPアドレスをDNSサーバーに問い合わせ、実際に送信されたメールサーバーのIPアドレスと比較することで、送信元メールアドレス(ドメイン)の詐称を判断します。
「DKIM」は送信するメールに電子署名を付与し、受信者が署名の検証を行うことで、信元メールアドレスの詐称やメール内容の改ざんを検知する仕組みです。
「DMARC」は「メールに表示されるメールアドレス(ドメイン)」と「SPF」「DKIM」の認証に合格したメールアドレス(ドメイン)が一致しているかを確認するものです。
それぞれの仕組みはともかく、重要なのはメール配信する際にこれらの認証を行っていないと迷惑メールとして扱われ、そもそも見込み客に届かない場合があることです。(例えばGmailは2024年2月からDMARCに対応していないメールを迷惑メールとして扱うようになっています)
「SPF」と「DKIM」はいずれも「送信元サーバーやメール内容の正当性を保証する」ものですので、どちらか一方の認証で問題ありません。メール配信する際には「SPF」「DKIM」のいずれか、および「DMARC」の認証を必ず行いましょう。
⑤効果測定および検証、改善
メールを配信した後は、最初に決めた目標の達成度を確認するために配信結果をチェックします。
メール配信システムを使用している場合、到達率、開封率、リンクのクリック率、コンバージョン率、購読解除率などを計測できます。
設定していたKPIよりも開封率が低かったならメールの件名を見直す、クリック率が低かったならCTAの設置位置を改善するといった工夫を行いましょう。
メールマーケティング導入の課題
メールマーケティングを始めるに合ったって直面する課題としては以下のようなものがあります。
- リストが集まらない
- 開封率やクリック率などの数値をうまく分析できない
リストが集まらない
前述の通り多くの企業で頭を悩ませているのが、リストの不足です。
株式会社リンクアンドパートナーズが行った「メールマーケティングに関する調査」でもメールマーケティングの課題として、29.8%が「リストの不足(正確なメールリストの維持)」を上げています。
出典:【メールマーケティングに関する調査】課題として「効果が出ない」という回答が最多に(PRTIMES - 2023年11月)
この課題はメールマーケティングの担当者一人で解決できるものではありません。
マーケティングチームひいては会社全体の課題としてとらえ、対策する必要があります。
メールアドレス獲得の具体的な手法としては、営業部にセミナーで積極的に名刺交換を行ってもらう、SEO対策や広告運用を行いWebサイトの登録者数を増やすなどの方法があります。
ただ、メールアドレスは個人情報ですのでメリットなしで簡単に登録してもらえるものではありません。
Webサイトの会員登録「詳細な調査レポートをダウンロードできる」「定期的にクーポンがもらえる」「会員限定機能の開放」といった付加価値の提供が不可欠です。
また、会員登録時に詳細に見込みの情報を収集できれば、セグメント分けを的確に行うことができるので、見込みの一人一人に合ったきめ細やかな施策を実施できます。
ただし、会員登録時の入力項目が多くなってしまうため、入力画面での離脱率も高くなってしまいます。
「企業名」のような個人を特定につながりそうな情報は、入力のハードルになることがあります。
入力項目の数はできるだけ少なくしたうえで、内容も「業界名」や「部署名」などといった、セグメント分けをするのに十分な情報を得られる項目に限定するようにしましょう。
さらに、営業部が保有する名刺をリスト化する場合にも課題となる点があります。
例えば、名刺をスキャナーで取り込む場合、表記ゆれが発生しますし、名刺の情報だけでは、過去の取引・商談の内容など詳細な顧客情報は登録することができません。
質の高いメール施策を実施するためには、営業担当者が持っている情報を余すところなく登録する必要があるため、登録作業の協力を取り付けなくてはなりません。
登録作業がマーケティング施策のためだけではなく、営業部門の業績改善にもつながるような仕組み作りとその周知も重要です。
開封率やクリック率などの数値をうまく分析できない
こちらの課題は「メール配信システム」を利用していない場合に直面します。
メールマーケティングのうち、メルマガの配信を行うだけなら「メール配信システム」を使わずとも行えます。
ただし、その場合は「開封率」「クリック率」などの効果測定が困難になります。
効果測定ができなければ、施策を改善することもできませんので、次項で説明するいずれかの方法を使用しましょう。
メールマーケティングに使うツール
メールマーケティングの効果測定を行う方法は、大きく分けて3つあります。
- メール配信システムを使う
- Google Analytics(GA4)を使う
- MA(マーケティングオートメーション)
メール配信システムを使う
最も簡単に効果測定する方法は「メール配信システム」を使うことです。
メール配信システムの機能としては以下のような機能あります。
- 到達率のチェック
- 開封率のチェック
- クリック率のチェック
- コンバージョン率のチェック
- 購読解除率のチェック
- ステップメールの自動配信
- シナリオメールの自動配信
「メール配信システム」を使えば、効果測定が行えるほか、ステップメールやシナリオメールの配信を行えるようになります。
ただ、通常のメール配信システムでは難しいこともいくつかあります。
- リンククリック後のWebサイトでの行動追跡
- 関心度の高い見込み顧客の自動抽出
メール配信を行うのには十分なツールではありますが、この2点には注意しておいてください。
Google Analytics(GA4)を使う
「メール配信システム」ではできなかった「リンククリック後のWebサイトでの行動追跡」を行えるのが、Google Analytics(GA4)を用いる方法です。
Google Analytics(GA4)をメールマーケティングに使う場合、測定できる内容は以下通りです。
- 到達率
- 開封率
- クリック率
- コンバージョン率
- リンククリック後のWebサイトでの行動
ただ、メールの作成に知識と手間がかかるうえに、HTMLメールでしか利用できないので、そのためのツールや知識も必要になります。
また、ステップメールやシナリオメールの配信は行えませんし、関心度の高い見込み顧客の自動抽出といったこともできません。
あくまで、効果測定のためのツールとして使用することになります。
MAを使う
MA(マーケティングオートメーション)は導入コストがやや高くなりますが、「メール配信システム」「Google Analytics」で行えることはほぼ全て実現できます。
大規模にマーケティング施策を行いたい場合はこちらがおすすめです。
配信のための機能や効果測定はもちろん、関心度の高い見込み顧客の自動抽出できるため、営業部門への受け渡しや他のマーケティング施策を行う際のリスト作成にも大いに役立ちます。
高機能なものを使いこなせない場合は、導入後のサポートが充実しているツールを選ぶとよいでしょう。
